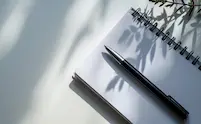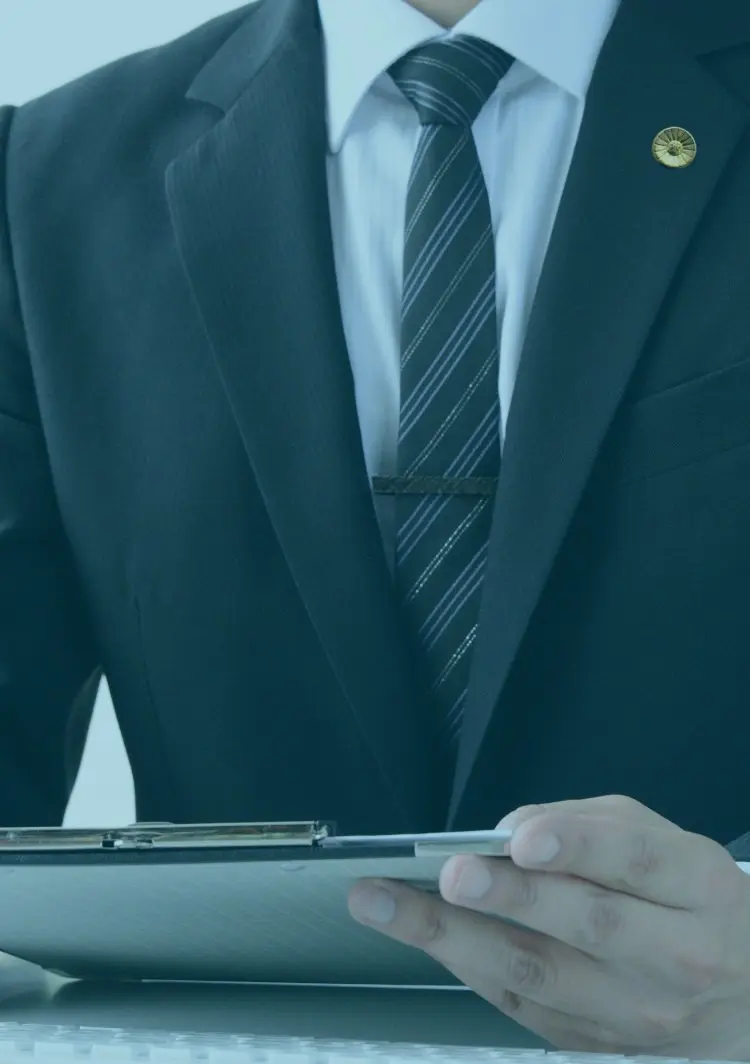弁護士 内藤 幸徳
東京弁護士会
この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳
東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員副委員長。 祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 また、賠償責任の実績が多く、特に交通事故は、年間200件を超える対応実績がある。 医療機関の法務に強く、医療・法務の架け橋になれる弁護士として活動している。
交通事故でお怪我をされた場合、相手方に請求できる賠償額の費目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等が考えられます(1)。
これらのうち、最も高額になることが多いのは、入通院慰謝料です。
入通院慰謝料は、入院または通院しなくていけなくなったことにより生じる精神的苦痛を填補するための慰謝料であり、入通院期間に応じて、賠償額が決まります。
入通院慰謝料の計算方法として
- 自賠責法で定める自賠責基準
- 任意保険会社が独自で定める任意保険会社基準
- 裁判で定められる裁判基準(弁護士基準とも言います。)
の3つがあり、①<②<③の順で金額が大きくなります。
具体的には、
という計算式で計算されます(2)。
例えば、事故が10月1日、治療終了日は12月1日、その間に10日間通院した場合を想定します。
この場合
となるのに対し、
となります。
交通事故の実務として、弁護士が介入しない場合、入通院慰謝料が③裁判基準で計算されることはほとんどありません。つまり、入通院慰謝料について、裁判に準じた適正な水準の賠償を受けるには、弁護士にする他ない、ということになります。
既に相手方保険会社から賠償額の提示がある場合でも、弁護士委任をすれば、賠償額の増額交渉が可能となります。
適正な賠償を受けるため、弁護士委任をご検討ください。
*2 入院がなく、通院だけの場合です。裁判基準はむちうち、軽傷の場合の基準であり、骨折等では金額が異なります。なお、通院頻度が少ないと、実通院日数の3倍程度で計算されることがあります。